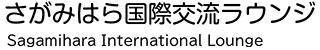行事レポート (通訳実務研修 教育編)
ボランティアのための学校通訳に関する実務研修会を開催しました!
さがみはら国際交流ラウンジは、9月13日(土)、相模原市立図書館・2階視聴覚室において、一般社団法人日本公共通訳支援協会講師(スペイン語通訳者)の霜村由美子(しもむらゆみこ)さんを講師にお迎えして、学校通訳に関する実務研修会を開催しました。この研修会には、通訳・翻訳ボランティアに関心のある相模原市民など30名が参加しました。
研修会では、前半は霜村先生による学校通訳における心得と基礎知識について、講義を行っていただき、後半は言語別(英語、中国語、フランス語)のグループに分かれて、学校通訳の現場を想定したロールプレイを行いました。
前半の霜村先生の講義では、学校通訳の特徴として、(1)支援業務(生徒や保護者が日本の学校になじめるように外国語により支援を行う)と通訳業務(異なる言語を話す人の間でそれぞれの言葉に訳して相手に伝える)の混同が起こりやすいこと、(2)小中学校(義務教育であるため退学はない)での通訳と高校(定められた出席時数、単位数を満たない場合は進級や卒業ができない)での通訳が異なることなどに留意して通訳を行う必要があると述べました。
また、通訳においては、(1)通訳に必要な語学力がある(聴解力、専門用語)、(2)相手の話を理解する(内容に関する基礎知識、背景知識)、(3)聞いたことを正確に記憶する(短期記憶力)、(4)聞いたことを正確に別の言語に置き換える(語彙、作文力)などのスキルの向上を目指すとともに、通訳の心構えとして、「メカジキ」(メ:メモ取り、カ:会話止め、ジ:辞書引き、キ:聞き返し)が、大切であることを教えていただきました。
後半のロールプレイでは、霜村先生の指導の下で、言語別に3人一組のグループになり、各々が外国人生徒の父兄、担任の先生、通訳の役を演じながら、学校通訳の現場を疑似体験することで、実際に学校通訳を行う際に適切に対応できるよう学習しました。研修会参加者のほぼ全員が未経験であったことから、学校通訳の難しさを痛感しつつも、ロールプレイに真剣に取り組む姿勢がとても印象的でした。
質疑応答では、参加者から、通訳の最中に通訳能力に不足を感じた際の対応、解らない言葉や専門用語があった場合の対応、通訳業務を行う際に適切と思われる辞書媒体(紙媒体、電子辞書、WEB翻訳等)、通訳ボランティアになるための学習方法、海外における教育者の社会的地位などについて質問が寄せられました。霜村先生はこれらの質問に対して詳細、且つ、丁寧に回答されていました。 相模原市の外国籍の住民は、昨年、初めて20,000人を超えました。このような状況もあって、さがみはら国際交流ラウンジでは、教育現場での通訳をはじめ、医療、生活支援、防災、国際交流の現場で、活動していただける通訳・翻訳ボランティアを募集しております。また、通訳実務研修会は年に2回(教育編・医療編)開催しています。次回、皆様の参加を期待しております。
以上